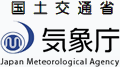長官会見要旨(令和7年10月15日)
会見日時等
令和7年10月15日 14時00分~14時45分
於:気象庁記者会見室
発言要旨
冒頭、私から、4点述べさせていただきます。
まずは、台風第22号、第23号及びその間にあった気象衛星ひまわりの障害についてお話いたします。
相次ぐ台風の接近により伊豆諸島を中心に大荒れの天気となった件についてですが、まず、今回の台風により被害にあわれた方々に、心よりお見舞い申し上げます。
台風第22号についてですが、10月8日から9日にかけて、非常に強い勢力を保ちながら伊豆諸島に接近することが予想されたことから、8日に東京都伊豆諸島に暴風、波浪の特別警報を発表しました。実際に、八丈島では10月9日明け方、5時24分に、最大瞬間風速54.7メートルの猛烈な風を観測したところです。雨についてですが、台風本体の雨雲の影響で、9日明け方から朝にかけて伊豆諸島で線状降水帯が発生し、記録的な大雨となり大雨災害の危険度が非常に高まったことから、9日、6時20分に東京都伊豆諸島に大雨特別警報を発表しました。
また、台風第22号に続いて、13日にかけて、台風第23号も伊豆諸島へ接近し、八丈島や青ヶ島などの被災地でも再び暴風や大雨となりました。
この間、気象庁においては、自治体とのホットラインの実施や、八丈町などにJETTを派遣するなどして、自治体に気象台が持つ危機感を適切に伝えてまいりました。
一方、台風第23号の監視の最中に静止気象衛星「ひまわり9号」の障害が発生しました。これについては「ひまわり8号」への切り替えにより、影響は最小限とすることができました。改めて静止気象衛星の2機体制の重要性を認識したところです。「ひまわり9号」については、復旧作業を行い、すでにデータは取得できておりますが、現在引き続き、障害の原因の調査を行い、運用の確実性を確認しています。
また、9月の大雨についてですが、9月も前線や低気圧の影響で、北日本を中心に大雨となりました。特に9月20日から21日にかけて、前線を伴った低気圧が発達しながら北海道付近を通過した影響で、北日本を中心に暴風や大雨となり、北海道の釧路地方、十勝地方では21日明け方に線状降水帯が発生するなど、記録的な大雨となりました。北海道で線状降水帯が発生したと発表したのはこれが初めてです。このように線状降水帯が北日本でも発生するようになってきましたので、こうした事例をしっかりと振り返り、引き続き、精度向上に努めてまいりたいと思います。
それから、線状降水帯の半日前予測の結果でございますが、今年度10月9日時点で、都道府県ごとの集計で86回の発表のうち、実際に線状降水帯が発生した事例が12事例となっておりまして、約14%の適中率と当初の想定よりも低くなっています。また、線状降水帯が発生した事例はこれまでに全部で17事例ありましたが、事前に予測情報が発表できなった事例が5事例となっておりまして、捕捉率は71%と当初の想定よりも大きく上回っているところです。
なお、線状降水帯の半日前予測の情報を発表した場合には、その約6割が3時間降水量100ミリを超えておりまして、被害が生じるような相当量の大雨になっています。このため、この半日前予測の情報を見聞きした場合には、大雨災害への心構えを一段高めていただくことが大切です。
気象庁としては、引き続きしっかりと気象状況の監視・予測を行い、線状降水帯の情報も含めまして、適時適確な防災気象情報の発表に努めてまいります。
次に2点目ですが、10月の気象等の注意喚起でございます。
秋にもなりますと行楽を楽しむ方も多くなると思いますが、天気の急変にも十分に備えて頂くようにお願いします。特に登山の場合、山頂は低温となっていることもありますので、低体温症など思わぬ事態となることもあります。出かける前や、お出かけ先でも気象情報を確認して頂き、十分な準備をお願いするとともに、登山の道中空の様子にも注意してください。もちろん、火山の場合には噴火警戒レベルや解説情報が出ていないか、事前の確認をお願いします。
台風については、先月の会見でもお話しました通り、強い勢力で日本にやって来る時期ですので、引き続き、台風情報について、最新の情報を確認いただくようにお願いします。
また、季節の変わり目では、これまで覆われていた暖かい湿った空気と、少しずつ南下する大陸の冷たい空気に、天気の周期変化に応じて、交互に覆われることになり、気温の変化が激しくなります。体調を崩しやすい季節でもありますので、ご留意ください。
次に3つ目、緊急地震速報訓練についてでございます。
気象庁では、内閣府・消防庁とともに、緊急地震速報を見聞きした際の行動を確認するための、全国的な訓練を来月11月5日に実施します。
緊急地震速報は、見聞きしてから強い揺れに襲われるまでの時間がごくわずかであり、その短い時間に、慌てずに身を守るなどの防災対応をとるためには、日頃からの訓練を通して実際に行動をとり、経験することが重要です。
このたび、専用の設備が無くても簡単に訓練を行うことができるツールとして、スマートフォンなどでご覧いただける動画を新たに公開しました。動画を再生すると、カウントダウンのあと、実際の緊急地震速報の音が鳴りますので、それを合図に身を守る行動をとっていただける内容となっております。ご都合の良いタイミングでご利用いただけますので、個人やご家庭での訓練のほか、学校のクラス単位での訓練などにもご活用いただけると考えております。気象庁ホームページのトップにある、「最新の取り組み」でも紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
4点目は地震火山の基本的な知識の普及啓発についてです。
9月の会見で申し上げましたとおり、気象庁は、科学的根拠に基づく情報とそうでない情報を見極めるための、基本的な知識の普及啓発を強化する取組を進めます。
地震や津波、火山噴火の基本的な知識、また、気象庁の防災情報を活用いただくうえで重要ではありますが、広く一般には浸透していない知識について、整理を行ったのちに気象庁ホームページにおいて公開してまいります。現在、準備を進めているところであり、来月を目途に、順次公開していく予定です。
報道機関の皆様におかれても引き続き、普及啓発へのご協力をお願い申し上げます。
私からは以上です。
質疑応答
Q:幹事社から最初に冒頭質問させていただきます。4本ほどありますので、よろしくお願いします。まず1つ目ですけども、今回伊豆諸島に接近した台風22号および23号ですが、特に22号に関しましては高い海水温などが原因で想定以上に勢力が衰えなかったことが、特別警報に至った面があると思います。人的被害などは幸いない中で今回も断水など復旧のめどが立たない部分もありますが、改めて一連の対応について受け止めをお願いします。
A:10月5日3時に小笠原近海で発生した台風第22号は、急速に発達し、非常に強い勢力を保ちながら、伊豆諸島に接近、通過することが予想されたことから、気象庁では、台風が接近する前の10月8日夕方に暴風、波浪特別警報を発表し、最大級の警戒を呼びかけておりました。また、線状降水帯が発生する恐れがあることから、半日前予測を行うとともに、線状降水帯が発生した場合には、局地的に雨量がさらに増えることや、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性について言及し、大雨災害に対する備えを呼びかけていたところでございます。実際に台風が接近した伊豆諸島では猛烈な風を観測し、海上は猛烈なしけとなりました。また、台風本体の雨雲の影響で、9日明け方から朝にかけて、伊豆諸島では線状降水帯が発生し、観測史上1位の値を更新する記録的な大雨となりました。この雨により大雨災害の危険度が非常に高まったことから、10月9日には東京都伊豆諸島の八丈町に大雨特別警報を発表したところでございます。一連の対応を振り返りますと、今回の台風に対する注意、警戒については事前の呼びかけ、それからジェット派遣などにより、気象台が持つ危機感というのは十分に自治体や住民の皆様にお伝えできたのではないかと考えています。現地の住民の皆さんの避難の状況なども拝見いたしますと、そういう効果が十分あったのではないかと考えているところでございます。
気象庁では、台風が接近する前から段階的に気象情報を発表するとともに、災害の危険度の高まりに応じて気象警報や注意報を発表し、台風に対する備えを呼びかけておりますが、今回のように、日本の近海で急激に発達するような台風が接近、通過する場合もございます。テレビのニュースなどで台風について取り上げられているようなときには、こまめに最新の気象情報を入手していただき、適切な避難行動に繋げていただければと思います。
また、海水温も一つの要因だとは思いますけれども、日本周辺の海面水温が平年よりも高くなっております。それが発達に十分寄与したことは、確かだと思います。それ以外にもいろいろと大気力学的なことも含めて、条件が整いますと、近海で急激に発達することがあります。発生してから日数たたずに、陸地に来ることもありますので、最新の予報を見ていただければと思うところです。また、日本の南海上は未だに、対流活動が活発な時期で、まだ台風が発生することもあろうかと思いますので、十分に注意していただければと思います。
Q:冒頭でも触れられましたが先月21日に北海道で初めて線状降水帯が発生しましたが、これもこの要因として北海道の南の海水温が平年より高かったことが、挙げられていると思います。こうしたこの北海道でも線状降水帯が発生するようになった状況が日本の異常気象が進行していると感じるところでもあるのですけれども、改めて受け止めの方、よろしくお願いします。
A:今年の出水期を振り返りますと8月から9月にかけて、北海道や東北地方、東北地方では特に秋田県に大雨の被害がありましたけれども、勢力の強い太平洋高気圧から暖かく湿った空気が流れ込んで、低気圧の通過が多かった影響によりまして、記録的な大雨が複数回発生するなど、例年、大雨が降りやすい西日本に限らず、北日本でも大雨となった年となりました。今回の夏の高温の原因のところの説明でもありました通り、日本付近は高気圧に覆われて、偏西風が北寄りを通ったことによりまして、低気圧が発達しやすい通り道も北寄りになったうえに、その南側には湿った空気がありましたから、その空気が流れ込んで大雨となったということでございます。それによって、北海道、それから秋田県で度重なる洪水があったと記憶しております。そういう意味で、これから北日本においても、大雨というのは十分警戒する必要があるだろうと思っております。北海道での初めての線状降水帯ということでご質問いただきましたけれども、これまでも、北海道では平成26年9月に大雨があったりしましたが、今回は線状降水帯の大雨になりました。積乱雲など強い対流活動によって雨が降るという傾向は南の地域の雨の降り方ですが、そういうのが北日本でも起こるようになってきたということで、長いスケールの変化があるのかもしれません。ただ、まだそこは確実なことは言えませんので、異常気象が進んでいるのかどうか確かめるためにも、今後北日本での雨の降り方の変化ということは注意をしていきたいと思います。また、海水温のことも、海洋の熱波と言われておりますので、これも研究も含めてしっかりと見ていきたいと思いますし、我々海洋気象観測船を持っておりますので、しっかりと観測していきたいと思います。いずれにしろ、大雨が頻発した今年の夏の状況を考えるに、過去の気候と変わってきていますので、そういうことを念頭に、いろんな分野の方々についても、これまでの経験だけで判断して過ごすことはやめた方が良いのではないかという気がしているところです。
Q:次の質問なのですけれども、今年の夏暑かったというところで、今ちょっと暑さはだいぶ和らいできたかと思うのですけれど、総務省の方から令和7年5月1日から9月28日の熱中症による救急搬送者数が、速報値で10万人を超えたというのが、初めて超えたということが発表されていましたが、救急の現場が今年もかなり負担が大きかったという声もありますが、改めて今年の暑さに関する受け止めをお願いします。
A:今年は暑さについて、非常に気温も高かったということがございますが、梅雨の時期も晴れ間が多くて、そういう意味では暑い期間も長かったと考えております。これについては皆さんご案内の通り9月9日に異常気象分析検討会を開催しまして、専門家の先生方に分析をしていただきましたけれども、アジアの熱帯域での積乱雲の発生が活発だったということで、その上昇気流の裏返しの形で日本付近の下降気流が強まって高気圧が強まったことが主な要因と指摘されております。こういう状況が来年以降も起こるかわかりませんけれども、地球温暖化によって長期的に大気や海洋に熱が蓄積され続けていることも記録的な暑さの一因でありまして、今後も確実に強まっていくと考えております。そうしますと先ほど申し上げた通り、過去の気候とは異なる気候になってきておりますので、これまでの常識、つまりこの時期になったらこうなるだろう、これでいいだろうという心構えでは、対応しきれないことも多々増えてくると思いますので、そういう意味でどういうふうに適用すればいいかという準備をいろんな分野の方々にはお願いしたいと思います。我々も、どのように変わっていくのかという情報を出していくことが対策をする方々への支援だと思いますし、そういうシミュレーションやデータを、積極的に使いやすいようにして、皆さんに貢献していきたいと思っています。
Q:最後の質問となります。先月の3ヶ月予報の際に10月は全国的に気温が高くなる見通しも示される中で、この後秋にかけて逆に秋が短くて、急に冬が来るみたいなところもあったと思うのですけれど、今日なんかは肌寒いところもあると思うのですけれど、秋にかけての体調管理等への呼びかけをお願いします。
A:まず、まだ暑い状況も続いています。今月12日には鹿児島で、猛暑日となりました。東日本、西日本、沖縄、奄美は、依然として、かなり気温が高い状況で経過しているところです。そうは言っても実際秋ですので、涼しさに体が慣れていく中で、時に暑い日が訪れるということがありまして、極端な気温差が体に負担となることがあろうかと思います。これから冬にかけては、10月前半までは平年よりも高く経過していきますけども、来週は北日本中心に低くなる見込みで、他の地域でも12月になりますと寒気が流れ込みやすく、平年並みか低い予想となっております。こちらについても急激な気温の変化により体調を崩しやすくなりますので、体調の管理には十分ご注意いただきたいと思います。具体的にはどの時期に寒気が流れ込むかっていうのは3ヶ月予報では、予測できませんので、近づいてきたら1ヶ月予報や2週間気温予報などをご覧いただければと思います。先ほど申し上げた通り、現在もですね、東日本、西日本のあたりまでは暖かく湿った空気がありますが、大陸の方からは非常に乾いた冷たい空気も降りてきておりますので、大気の流れによって、寒くなったり暑くなったり、差も大きいですし、時間のスケールも短い間に変わりますので、そういう意味でも、お体に気をつけていただきたいと思います。暖房器具なども出せるようにしておいたらよろしいかと思っております。
Q:冒頭あった線状降水帯の半日前予測の実績に関して伺いたいのですけれども、今日時点で適中率が約14%ということで、時期的に考えると、ここから、想定の25%に上がるまで行く可能性は低いと思うのですけれども、そうすると昨年に続いて運用前に想定していた25%に達しないということになると思うのですけれど、その点について、線状降水帯にはならなくても大雨になっている確率が高いというお話もありましたけれども、2年連続で、まず事前の想定に達しなさそうということの受け止めですね。問題だというふうに考えていらっしゃるのか、それと今後ですね、どうすれば上げていけると考えていらっしゃるのか。あとはその難しさに関して、まず教えてください。
A:雨の予想の成績というのはいろんな指標がありまして、適中率というのは、予報出したうち、どれだけ当たったかということで、これが低いということは空振りが多いということになります。その裏返しで捕捉率は今日の段階で、71%になっていますけれども、捕捉率というのは実際降ったものについて、ちゃんと予報していたかということなので、これは高い状態ということになります。我々としては、防災上はやっぱり見逃しということは避けたいと思っています。空振りについてはもちろん、オオカミ少年にならないように空振りを下げなければいけませんが、見逃しを減らすということをまず優先して、現在こういう状態になっている部分はございます。こうした現状について、直ちに非常にまずい状況だとは考えておりません。あと、仰っていただいた通り、予測した際に3時間で100ミリ以上の大雨になって状況も60%ございます。大雨の発生は予測できていることになりますが、線状降水帯予測は大雨の発生だけではなくその形態も当てなければいけないところもありまして、これは長時間決まったところに留まることの危なさを表す意味で重要なのですけれども、この形態を予測する難しさも考慮に入れますと、25%に達していないにしても、それなりの結果にはなっているのではないかという認識です。非常に甘いと言われるかもしれませんけれども。それから、改善の新しいスキームも随時入れていまして、例えば、メソアンサンブル予報の活用ですとか、局地モデルの導入、それから予報官による資料活用上の工夫、それから、アメダスに湿度観測を追加したり、洋上でのGNSSの観測なども入れて、シミュレーションに同化やその工夫をしていくことも行っています。確かに空振りが多いという適中率の低さはありますけれども、そういう改善を積み重ねることによって、適中率の低さは解決していくと思っております。楽観的とご批判されるかもしれませんけれど、自分としてはそう考えているところです。
Q:冒頭のご発言にもありましたひまわり9号の観測障害について伺います。9号の障害についてはですね、昨年に続いて2度目となるかと思います。これについて受け止めを改めてお願いします。
A:昨年も、トラブルがあって、年数経たないうちに、今回こういうことになったという意味において、これはちょっと原因究明をしっかりと行うべきだと考えております。先ほど申し上げた通り8号はその日のうちにスタートして運用していますが、実は、8号が動いて、そのすぐ後に9号も動き出して観測はしているところですけれども、9号にすぐ戻さない理由は、まさに原因をしっかりと調べて、それからある期間走らせて、いろんな雑音が出ないかどうかしっかり確かめた上で戻したいということによるものです。おっしゃる通り、短期間で2回目ということで、前回とは異なる種類のトラブルではございますけれども、やはり慎重に戻しはやっていきたいと思います。この2機体制については、今度の10号の打ち上げが5年後ということになりますので、令和12年ということで、まだまだ期間がありますので、今からこの上に行って直すというわけにもいきませんけれども、原因をしっかり把握したうえで、例えば運用の仕方でトラブルを避けるようなことができるのであれば、そういう工夫もあると考えています。慎重に対応していきたいと思っております。
Q:ひまわりを巡ってはですね、今お話があった10号の打ち上げが遅れたりですね、あと9号についてもトラブルがあって、というところで安定的な気象観測とかですね、火山の監視のためにはちょっと不安な要素を抱えているかと思うのですけれども、どのように対処していくおつもりであるか改めてお願いします。
A:衛星の場合は、補修しに行くわけにはいかないので、今上にある8号、9号で対応するしかございません。そういう意味では今申し上げた通り、運用の仕方など、どういう工夫ができるのかを考えていくということかと思います。10号の打ち上げの時期も後ろに行きましたし、また他の衛星を打ち上げるわけにもいきません。そういう意味では、2機体制でやっていますので、この使い方をうまくやることで、しっかりと10号が打ち上がるまで持たせるようにしていきたいと思っております。
Q:先ほどの質問の中にもありました半日前予測の適中率についてなのですけれども、完全に捉えること非常に難しい現象なのかと思いますけれども、この線状降水帯の予測が難しい要因についてのお考えと、それをどのように改善していけるかという点改めてお願いいたします。
A:元々難しいチャレンジングな取り組みではありますけれども、大雨を予測した地域で大雨となるかということも難しいというところですが、線状降水帯予測の場合、その形態まで当てなければいけないということで、大変難しいというところです。実は、線状降水帯と一言で言いますけども、いろんな種類の線状降水帯があります。今回のように台風の周りにある降水域での線状降水帯もあれば、湿った空気が集まる中で収束して出来上がる線状降水帯もあります。これらは原因が違うわけですがこうしたことも難しい要因です。今、集中的に研究や、観測の高度化などもしていますし、予報官がそれらのデータをどう使えば予報精度が上がっていくかということも検討していますので、しっかりと精度を上げていきたいと考えています。適中率は低いですけども、捕捉率はこれだけ上がってきています。予報の精度を表す指標の全部が悪いわけではございませんので、私は一定の成果が出てきていると思っています。それから、これに取り組み始めてから数年経ってですね、先ほど申し上げたメソアンサンブルの導入だとかいろんな改善を進めてきていますので、これからだんだん成果が上がってくると思います。今年よりも来年はさらに良くなると思います。それから最終的には、衛星が上がって赤外サウンダの利用技術もいろんな工夫があると思います。赤外サウンダもヨーロッパのセンターが今年あげました。静止気象衛星では初めてですが、これを使って観測する中で、世界中の研究者が、シミュレーションへの同化の仕方について、いろんな技術を磨いていくと思いますので、そういうことにも期待しながら、しっかりと高い精度をこれからも勝ち取る努力をしたいと思っています。
Q:ちょっと話は変わるのですけれども、今政府の方では連立政権の解消がありますし、それで国土交通大臣も今後全く別の政党の方とかに選ばれるのかなとは思うのですが、今後もし大臣がもう、例えば今まではもう30年ぐらい公明党の方がこうなってきたようなことを今度は別の政党とかになった場合に、この気象業務、気象庁として、その何か影響というのは何か予想されたりするのでしょうか。
A:正直申し上げて政治のことはよくわかりませんが、これまでの大臣には大変お世話になっておりますし、我々いろんな国会議員の方々に説明させていただいたりしますが、それぞれの考え方に関係なく、防災については、皆様重要だと、気象業務については本当に大事であり、応援していると言ってくださる方々がほとんどでございますので、ご指導内容は、引き続き、いろいろといただけると思っておりますし、我々としましては、どういう状況になろうとも、国民の命を守るという仕事は変わりませんので、今日も明日も明後日も、何かあれば我々の責務に応じて頑張っていきたいと思いますし、今後のいろんなご指導も全く変化なく、重要だというご認識でご指導いただけるものだと思っております。
Q:何度か質問もありましたひまわりに関連しまして、2機体制の重要性というお話がありましたけれども、ひまわり10号が1年遅れることで耐用年数とかも9号を超えて運用することになりますし、今のところ10号については10号だけをとりあえず打ち上げるという計画だと認識していますけれども、そこの辺りのバックアップは9号がするというところについての不安といいましょうか、トラブルについての懸念、そういったところをどう解消していくのか、この辺りお伺いできればと思います。
A:そういう意味でも9号で何が起こったのかということは、しっかりと調べて原因究明も行いたいと思います。今のところは今の計画を変えるようなものではないと思ってはおりますけれども、そういう先入観なしで9号の状態はしっかり調べていきたいと思っています。今回のだけではなく、前回のトラブルについても、治った後もどうだったのかということも含めて、しっかりと状況を把握していきたいと思っております。今の段階では、今の計画を変えるほどではないと思っていますが、それは今後調査した結果次第では考えなければいけないことがあればしっかりと考えていくということだと思います。
Q:もう1点、防災気象情報についてですね、また来年から大きく変わるということにもなりますけれども、今後の周知、これが非常に重要になってくると思います。法改正等も必要になってくると思いますけれども、その辺のスケジュールであるとか啓発について今の段階でどういうスケジュール感を考えていらっしゃるかどうか、どう取り組んでいきたいかこの辺りいかがでしょうか。
A:防災気象情報の改善については検討会の結論が昨年の6月に出て、大枠はそれをもとに、内容を変えずにいこうと思っています。ただ、実際運用において、我々とか、国土交通省の水管理・国土保全局の運用の現実感というのがありますので、どうすればいいのかという検討をしております。今とかなり変わりますので、伝えていただく報道機関の方や避難指示を出す自治体の方々など関係の方々には事前にこの情報体系の変更については、説明申し上げている通りでございます。これは引き続きやっていきますけれども、今後より具体的になってきたら、住民の皆様への周知というのも重要かと思っています。我々自身もそうですが、自治体の皆様のお役目もあると思いますので、十分連携して、次の出水期に間に合うように準備しているところでございます。この周知が多分一番重要だと思っています。法改正については、必要かどうか、それから法改正をもしするのであれば、国会の状況に関連する部分もありますので、引き続き、我々としては、来年出水期にできるように、状況に応じて、しっかりと準備してまいりたいと思っています。
Q:先ほどの線状降水帯の件なのですけれども、捕捉率は高いのですけれど、やはり空振りがあると、どうせ出ても大丈夫だろうという人も増えるわけですし、さっきおっしゃったように3時間に100ミリ以上は結構6割あったのでいいという、それは確かにそうなのですけれど、逆に言うと、むしろそっちの方が目の前で雨が大雨が降るかっていう、その1人ひとりの感覚からすると大事で、線状降水帯はもしかしたら外れるかもしれないのだとしたら、何か私もどうすればいいかよくわかんないのですけれど、伝え方にもうちょっとその線状降水帯の工夫が必要なのかなと思うのですが、改めてそのあたりはどうでしょうか。
A:おっしゃる通り、線状降水帯に限らず、まさに大雨だけ追いかければいいじゃないかっていうご質問だと思います。先日の台風でも線状降水帯によって大雨特別警報も出ました。当初、あの台風の周辺の雨雲による大雨はそこまではいかないと我々見ていましたけれども、実際線状降水帯が発生すると、桁違いに降水量が上がるということで、その線状降水帯の怖さ、そしてまた予測しなければいけないという必要性は非常に高いと考えています。ですので今精度がこれだから、ぼやかして大雨の予想だけにすればということにはならないかと考えています。やはり線状降水帯の予測精度向上を目指さなければいけないと思っております。皆様から毎月ご批判を受けておりますが、これも承知の上でですね、引き続き、線状降水帯を対象に予測をしてまいりたいと思いますし、それに合わせて、さまざまな手法をいろいろ考えるということを全庁的に、研究分野も、本庁の技術開発部門も、予報官も、観測も、全体で考えるということは、引き続きやっていきたいと思います。その重要性から、当てなきゃいけないという使命も含めて、この方針を続けていきたいと思います。
Q:それが全体の予測技術全体の底上げにも繋がるということでしょうか。
A:そういう意味では、今線状降水帯のためにやっていることは、台風の予測精度にも、大雨予測そのものにも貢献すると思いますし、非常に難しいものを追いかけていますので、副次的には全体的な予測の精度の向上には繋がると思います。
Q:あともう1つ、ひまわり9号なのですけれど、確かに2機体制で、途中から画像が見られるようになったのですけれど、とはいえその可視画像しか見えないところもあってですね、そういうときもあって、やはり特に台風なんかあるときに赤外画像が見られないというのはかなり大きなことではないかと思うのですが、その2機体制だから大丈夫だったという何か、何か安堵していいものなのかという気もするのですけれどいかがでしょうか。
A:そもそも衛星の仕組みから、スイッチを入れたらいろんな準備が進まないと動かないところですが、可視画像は比較的すぐ利用できるところです。他方、赤外の部分は周波数が短いものから、だんだん順番に見えてきて最後一番長いところが見えてくるものです。今回時間的に可視画像が朝から見えましたので、日中ほとんど可視画像でカバーすることができました。また、赤外については、実は夜22時の全体のリカバーを前に、午後5時ぐらいから見え始めていました。今回はたまたま、可視画像が見えなくなるところで赤外画像が見え始めたという状況で監視できる状態がつながった状況ではありました。今回、8号の立ち上げについては全く異常なく行われたわけですが、こうした起動の特性などを踏まえて、2機体制での引継ぎの仕方、立ち上がり方について、そこにもし工夫の余地があるのであれば、そうしたところを工夫することも検討したいと思います。
Q:10月の天候についてお伺いします。先ほどの寒くなったり暑くなったりを繰り返すような天気で、短時間に急激に気温差が出ることが予想されるとおっしゃいましたけど、農家とか農業関係について、改めて警戒すべきポイントを長官のお言葉で改めて教えていただけますでしょうか。
A:秋口には冷たい空気がやってくるわけで、寒くなったり、暑くなったり、というのは秋としては不思議じゃないのかもしれませんけれど、さっき申し上げた通り、いつもとちょっと違う天候になっているので、夏場もいつもと違いましたし、梅雨はあるかないかもわからないような状況でした。暑さもずっと9月になっても10月になっても続くということで、いつもと同じではないのですが、短期的には予報ができますから、急な変化については、天気予報をしっかり見ていただいて、農家の皆様は日頃からよく見ていただいていると思いますが、いつも以上にちょっと見ていただいて、明日の予報だけで準備間に合わないかもしれない場合は、週間予報を見ていただくなど、そこをしっかり見ていただいて、急に寒くなるようなときには、それに応じた対応の仕方が多分あると思いますのでしっかり対応していただければと思います。いつもと同じではなくて、いつも以上に気象情報をしっかり見ていただければと思います。
(以上)